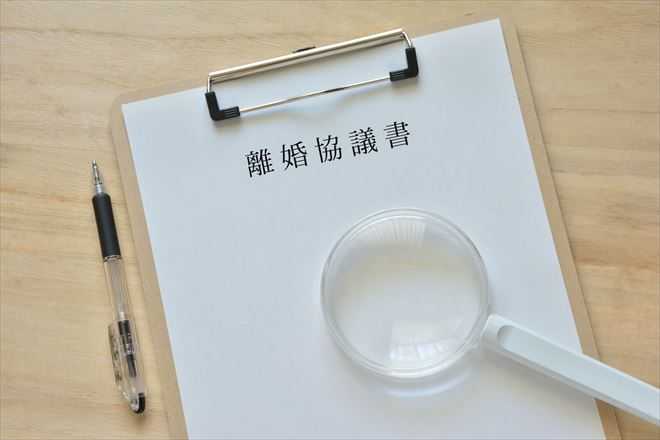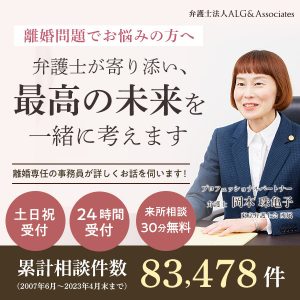協議離婚の進め方マニュアル!慰謝料や養育費は?平均期間は?
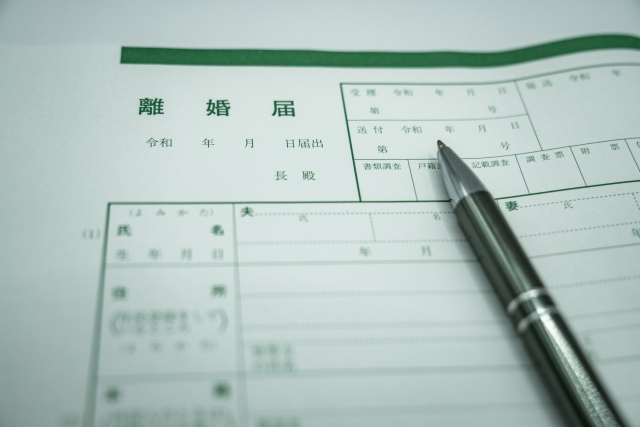
協議離婚は、夫婦間で離婚の条件などについて話し合い、合意に至ることで成立する離婚の形態です。裁判所を介さずに離婚が可能なため、円満な離婚を目指す際に有用な選択肢となります。
まず、協議離婚では夫婦で直接対話をすることになるため、互いの気持ちを十分に理解し合える点がメリットといえます。
もちろん家庭の状態にもよりますが、法廷を経る裁判離婚に比べ、穏やかな雰囲気の中で建設的な議論がしやすいといえばしやすいです。
さらに、手続き自体も裁判に比べてシンプルで、時間とコストを大幅に抑えられるのも協議離婚の利点です。
今回は、協議離婚の進め方、弁護士の代理交渉、慰謝料や養育費、平均期間について解説します。

- 全国対応
- 初回相談無料
- 土日対応可能
目次
「協議離婚」とは話し合いのこと
離婚に向けての話し合いの進め方は、主に「協議離婚、調停離婚、裁判離婚」の3つのステップに沿って進めていく事になります。
まず最初に行なう協議離婚とは、簡単に言うと「離婚について夫婦間でよく話し合う事」を言います。
つまり、裁判所を使わずに離婚する進め方は、すべて協議離婚となるのです。
協議離婚はどのくらいかかる?成立期間の平均相場は?
協議離婚の平均期間ですが、これについてはその夫婦によって最短も最長もピンキリです。進め方にもよるからです。協議離婚はあくまで裁判外の手続のため、公判のような期日が指定されません。
そのため、双方が多少でも歩み寄りの姿勢を見せなければ、1年や2年も協議中のままということもあります。
場合によっては、協議離婚中に復縁して離婚がなくなるケースもあるくらいです。
ただ、協議離婚が長引くと、精神的にも肉体的にも非常に疲れるため、離婚協議はできる限り早期に決着させることが、当事者双方にとってプラスとなります。
そのため、離婚を弁護士に相談すると、この協議離婚にかける時間は非常に短くなる傾向にあります。弁護士によっては、相手と一度接触してそれで話し合いに応じそうも無いと感じたら、すぐにでも次のステップである調停離婚に移行する手続をとる場合もあります。
離婚に強い弁護士からすると、相手方とちょっと話しただけで、この離婚が協議離婚で解決可能なケースなのか、協議に時間をかけるだけ無駄なケースなのかがすぐに判断できるのです。
そのため、協議離婚を早期に決着つけたいと考えた場合は、できる限り弁護士に依頼をして相手方と直接交渉してもらうと良いでしょう。
協議離婚で決めるべき・話し合うべきこと
協議離婚の進め方として、まず具体的に決めるべき・話し合うべきことは、大きく分けて以下の5つです。
- 財産分与
- 慰謝料
- 養育費
- 親権・監護権
- 面会交流
それぞれ、以下詳しく見ていきましょう。
①財産分与
財産分与とはその名の通り、夫婦が共同で築いた「財産」を分けることです。
ただ、離婚に伴って行なう財産分与はなにも現預金に限ったわけではなく、
- 住まいである自宅
- 家財
- 宝飾類
- ブランド品
などすべてにわたります。そのため、双方が納得できるような分け方を話し合って進めていく必要があります。なお、夫に収入があり妻が専業主婦の場合でも原則的には平等に2分割します。
その他、年金分割や退職金分割などもしっかり話し合いながら進める必要があります。
不動産・住宅ローンには注意
特に注意が必要なのが不動産関係です。
住宅ローンが残っている家庭も多いと思いますが、家を売却して半分にしようとしても「売却価格がローン残債を下回ってしまう」ケースもあります。
住宅ローンの問題については複雑なため、別途コラムに譲ります。併せて、ご参考ください。
②慰謝料
慰謝料は離婚に伴って必ず発生するものではありません。
どちらかに「不貞行為」「DV」などの離婚原因がある場合については、慰謝料を請求する事ができます。
この際の慰謝料の金額についても、一定の相場はあるものの、基本的には当事者間での話し合いで決まりますので、各家庭によって金額にバラツキがあります。
③養育費
養育費は離婚後の子供の生活費です(また特別費用というものもあります)。
- 毎月の負担額
- 学校や大学への進学にかかる費用
- 病気にかかった際の費用負担
などについても事前に進めながら取り決めておくことが重要です。
これらをあやふやなまま離婚してしまうと、親権者があとで苦労する事になります。
なお、後ほど少し説明致しますが、養育費については、再婚した場合や収入が減った場合などには「減額」が認められる場合もあります。 特に男性の方は、頭の片隅に留めておいてください。
④親権・監護権
親権は、単に子を引き取る権利のようにも理解されがちですが、それだけではありません。
親権は「監護権」と分離することもでき、もし実際に分離した場合は、親権は「法定代理人や財産管理をする権利」という扱いになり、監護権は「子供を引き取って養育する権利」という扱いになります。
ただ一般的には「監護権」は親権者に設定することが多くなっています。
⑤面会交流
面会交流とは、子を養育していない方の親が、定期的に子どもと面会を行うことです。これについても離婚する前に具体的に、いつ、どこで、どのくらいの頻度で子供と面会するのか、細かく取り決める事がとても大切です。
離婚後、できる限り相手方と話したくない、連絡をとりたくない、と思っている場合は、この面会交流をとにかく細かく取り決める事が重要となります。
例えば、連絡手段としてはメールと電話どちらを指定するのかや、誕生日やクリスマスに子供にプレゼントを渡す場合の詳細な手順など、細かすぎると思うかもしれませんが、このあたりは離婚してから話し合うと意見の食い違いが出てきて非常にストレスを感じる部分ですので、後から疑義が生じないよう、徹底して協議離婚の際に決めるようにしましょう。
当事者だけでは進まない!安い金額設定になる!ってホント?
いわゆる「円満離婚」というケースはほんの一握りにすぎません。
以上のような離婚条件に関する話し合いが当事者だけでスムーズに進むケースはほとんどありません。
また、適切な法律知識がないままこれらの条件を決めてしまうと、相場よりも安い金額設定になってしまうことも考えられます。
そのため、離婚する際にはできる限り協議離婚の段階から弁護士に相談して、弁護士に代理人として相手方と直接交渉してもらうと良いでしょう。
弁護士は「代理人型」と「後方支援型」、どちらがおすすめか
協議離婚で揉めることがあらかじめ、わかっている場合は弁護士に代理交渉してもらいます。
弁護士のサポートの仕方としては主に、
- 代理人型
- 後方支援型
の2通りがあります。
どちらもメリット・デメリットがありますので、自分の現在の環境にあわせて選ぶのが良いでしょう。それぞれの内容を少し詳しく見ていきましょう。
また、依頼を進める際には「離婚に強い弁護士」を選びましょう。

- 全国対応
- 初回相談無料
- 土日対応可能
①代理人型の特徴
代理人型は、話し合いを早期にまとめてしまいたい場合におすすめです。
依頼した弁護士本人にあなたの代理人となってもらい、以後は代理人弁護士が相手方と直接離婚協議を行なってくれます。あなたは弁護士に自分の希望する離婚条件を伝えるだけです。
この代理人型であれば、すでに別居状態のような場合でも問題なく離婚協議を進める事ができます。芸能人の離婚で例えると、高橋ジョージさんと三船美佳さんの離婚がまさにこの代理人型でした。相手方は代理人弁護士を立てられてしまうと、以降はその代理人弁護士を介して離婚協議を進めるしかありません。
代理人型のメリット(流れがスムーズ等)
- ①相手方と直接顔をあわせる必要がない
- ②すべてを弁護士に任せて自分は仕事や育児に集中できる
- ③相手方も話し合いに応じざるを得なくなる
- ④話し合いが早期にまとまり流れがスムーズ
代理人型のデメリット
- ①相手方の気持ちを刺激してしまうことになるため、相手方も弁護士を立ててくる可能性がある
- ②相手方が怒ってしまい、まとまりかけていた協議が振り出しにもどってしまう
②後方支援型の特徴
次は「後方支援型」についてです。
代理人型は協議離婚に関するあらゆる交渉や手続を弁護士が代わって行なってくれますが、後方支援型の場合は、あくまで本人がすべて対応する事になります。
その代わり、離婚条件に関する法的知識や金額の相場観、さらには話し合いにおいての注意点やコツなど、離婚協議に関するあらゆることを弁護士がアドバイスします。
後方支援型のメリット(弁護士費用が安い等)
- ①弁護士に相談していることを秘密にしたまま離婚協議ができるので、相手の神経を刺激せず、余計な対立構造をうまない
- ②弁護士費用を最小限に抑える事ができる
- ③離婚協議書など法的な書類関係の作成については弁護士に依頼できる
後方支援型のデメリット
- ①協議がいつまで経ってもまとまらない可能性がある
- ②すべて自分が主体となって行なうため大変である
例えば、協議離婚がまとまりかけていて、最後のチェックをしたくて弁護士に相談する場合や、弁護士を代理人として立てる程揉めていないようなケースについては、この後方支援型の依頼方法を選択すれば、余分な対立をさけられて、かつ、費用も節約することができるでしょう。
離婚の合意書|離婚協議書を作成する
無事、話し合いが進み、まとまったら、すぐに離婚届にハンコを押すわけではありません。まずは離婚の合意書「離婚協議書」を作成します。これは分かりやすく言うと「離婚契約書」のことです。
すなわち、どういう条件で離婚をするのか、協議離婚で話し合った内容を、もれなく記載し双方で署名捺印を行ないます。
それも大雑把に書くのではなく、例えば財産分与で不動産がある場合については、その不動産の所在地や地番、家屋番号などまで細かく記載します。
とにかく離婚した後に離婚協議書を見て一切の疑義が生じないようにする必要があるため、その精度は非常に重要となります。
そのため、離婚協議書は内容次第では非常に長い条文となりますので、通常は弁護士に依頼をして作成してもらいます。ネット上にはサンプルやテンプレート、雛形・フォーマット・文例などを見ながら、自分で作成することも可能は可能です。
またトラブルを回避するために、「公正証書」で作る人も多いことも頭の片隅に留めておいてください。
離婚届の記載の進め方|証人は必要だが誰にするか
離婚協議書の作成が終わったら、いよいよ離婚届を提出するわけですが、ここで最後のチェックポイントがあります。
既にお忘れかもしれませんが、離婚届には婚姻届と同じく「証人」が署名捺印する欄があります。証人はいらないということはなく必要です。
調停離婚や裁判離婚など裁判所が絡む離婚ではなく、当事者双方の話し合いによる「協議離婚によって離婚する場合は、離婚届に必ず証人の署名捺印が必要」となります。これは民法にも規定されています。
証人は誰でも可能。誰もいない場合は代行サービスを利用する。
証人は20歳以上であれば誰でもなる事ができ、家族に限らず職場の人や友人知人でも可能です。(当事者が兼ねることはできません)
ただ、婚姻届のときとは違い、離婚届の証人となると他人には頼みにくいものです。このような場合は、離婚を相談している担当弁護士や、証人代行サービスなどを利用すると良いでしょう。
法的な責任はないのか
誤解しがちですが「証人」と「保証人」は違います。
ここでの証人はあくまで離婚の見届け人というだけですので、証人として署名捺印したことで、何かしらの責任を負わされることはありませんのでご安心ください。
「離婚したい」という思いとどう向き合えば良いか?
今回は、協議離婚、特に弁護士に代理人となって交渉してもらう場合について、流れや抑えておきたいポイント、弁護士依頼のメリット・デメリット、慰謝料や財産分与、養育費との関係などについて紹介致しました。
離婚へ踏み切ることも、ただ惰性で離婚を回避することも、一時的な解決策にすぎないかもしれません。
しかし夫婦関係が修復不可能なほどに壊れてしまい、誰からのどのようなアドバイスも心に届かなくなってしまった場合、法的な観点での解決が必要となってきます。
まだまだ離婚することに迷う気持ちがあるなら、何度でもお互い歩み寄って、考え抜くというステップを踏み、その末に賢明な判断を行えるよう願うばかりです。人生の危機的な状況から抜け出すことができるよう切にお祈り申し上げます。