養育費の未払い回収に強い弁護士7選を紹介【おすすめ・口コミ評判】
養育費を払われず困っている全国の方々向けに、TwitterやGoogle口コミ評判が非常に高い回収・取り立て・強制執…[続きを読む]

養育費の強制執行・差し押さえを行いたい方は、デメリットはないのか、お金がとれない場合はどうなるのか、取り立てに失敗したら流れはどうなるのかとお考えかもしれません。
しかし、元旦那の養育費を払わない・未払いのまま、泣き寝入りしてしまうことはおすすめできません。
養育費は、子どもの健全な成長のために必要不可欠な費用ですので、義務者の取り立てからの逃げ得が許されてはいけません。
離婚した配偶者から援助がない状態が続いてしまっている方は、すぐに法律の専門家に相談しましょう。
今回は、養育費の強制執行手続きの流れ、公正証書のやり方、将来分はどうなるか、取り立てや差し押さえや申立方法、メリット・デメリット、差し押さえできる場合できない場合、お金がとれない場合、また相手が住所不明で会社がわからない場合は失敗するのかなどについて解説します。
なお、元配偶者から養育費の未払金を回収したい場合は、全国対応、着手金0円、成功報酬制の養育費の未払金回収に強い弁護士にご依頼ください。連絡先がわからなくても対応可能、元配偶者に会う必要もないなどのメリットがあります。

完全成功報酬制!相談無料!
完全成功報酬制!相談無料!
目次
やり方の前にまず、強制執行の定義は下記のとおりです。
たとえば、月々の養育費の支払が滞り、お金がとれなくなった場合、未払いの場合、強制執行の申立てをすることで、相手の財産から養育費を回収することができるというものです。
養育費の支払いについては、離婚時などに「公正証書」や「調停・審判」などで取り決めているはずです。
しかし、元配偶者が逃げて養育費が支払われなくなることも多いので、養育費を取り立てし回収をする手段として非常に有効な手段となります。
強制執行は失敗する、デメリットがある、お金がとれない場合があるという印象が強い方も多いでしょう。
強制執行については、民事執行法で詳細なルールが定められていますが、2020年4月1日から改正民事執行法が施行されています。
そのため、養育費などの強制執行が従来よりも利用しやすくなり失敗しにくくなっています。
こちらについて以下手続きの流れとともに詳しくは後述します。
養育費の支払いが滞ったからといって直ちに強制執行ができるわけではありません。強制執行するためには、以下で説明する要件を満たす必要があり、デメリットとまではいきませんが、お金がとれないケースがあることをしって、やり方を学んでいきましょう。
強制執行をするためには、「債務名義(さいむめいぎ)」を取得していることが必要です。
債務名義とは、債権の存在や範囲を公的に証明した文書のことをいいます。たとえば、「毎月〇万円の養育費の支払い義務がある」ということを公的に認めた文書のことで、下記のようなものがあります。
上記の文書は、ほとんどは裁判所で作成する文書です。
つまり単に、当事者が養育費の支払いについて合意をしただけの契約書では債務名義にはならないことに注意すべきです。
裁判所以外で作成できる債務名義は「公正証書」だけです。
また、公正証書であればなんでもよいというわけではなく、「執行認諾文言付き公正証書」でなければ差し押さえできません。
執行認諾文言付き公正証書とは、公正証書の条項で下記のような一文が入っているものをいいます。
これが入っているか否かで強制執行できるかどうかが変わってきますし、養育費の公正証書を作成しようとするときは、必ず執行認諾文言が入っているかを確認するようにしてください。
「執行認諾文言付き公正証書なんて知らなかった!」「離婚時にこんなデメリットがあるなんて知らなかった」と思う方もいるかもしれません。
当事者同士の契約書しかない場合は、差し押さえできないのでしょうか?お金がとれない場合が多いのでしょうか?
執行認諾文言のない公正証書や、当事者同士で作成した契約書等の場合は、強制執行の前に「訴訟等を行い、別途債務名義」を手に入れることで可能になります。
デメリットで困ってる方などは、詳しくは養育費回収に強い弁護士・未払いに強い弁護士などに相談するのが良いでしょう。
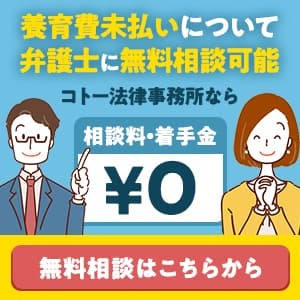
完全成功報酬制!相談無料!
完全成功報酬制!相談無料!
強制執行の対象となる代表的な財産としては、土地建物などの不動産、現金や高価な貴金属美術品などの動産、預貯金や給料などの債権などがあります。
ただ、裁判所が相手の財産を勝手に見つけて差し押さえてくれるというわけでありません。
強制執行の対象となる財産を「申立人の側で特定」する必要があります。
たとえば、給料を差し押さえるのであれば「会社」を特定し、預貯金を差し押さえるのであれば「金融機関と支店」を特定する必要があります。
もっとも、夫婦だったからといて、元配偶者の財産をすべて把握しているわけではないでしょう。
離婚後、元配偶者が転職・退職していた場合には、会社がわからないということも珍しくなく、お金がとれない場合もあるでしょう。
しかし、2020年4月に民事執行法が改正されたことにより、相手の財産の特定が容易になり、従来よりも強制執行の手続きが利用しやすくなり失敗しにくくなりました。
養育費の強制執行をするにあたっては、相手の財産を特定しなければならないというのが大きなハードルとなっていました。お金がとれない場合、失敗する場合もあり、大きなデメリットがありました。
しかし、民事執行法が改正されたことにより、相手の財産を特定するための「財産開示制度」の実効性が向上されました。
「財産開示制度」とは、債務者に対して強制執行の対象となる「財産に関する情報を開示」させるための手続きです。
従来の財産開示制度には以下のようなデメリットがあり、実際にはあまり使えない制度でした。
これに対し、改正後の財産開示制度では、以下のように従来の制度の欠陥・デメリットが改善されました。
これによって、相手の財産を把握することが可能になり、養育費の強制執行が容易になりました。
強制執行・差し押さえがどのように使いやすくなったか、詳しくはこちらの記事で解説しています。
養育費の差し押さえの流れ・手続き、やり方、強制執行の申立てはどのように行えばよいのでしょうか。以下では、強制執行の申立てに必要な書類や流れについて説明します。
まず、以下の必要書類と手数料を用意します。
| 申立書 | 表紙、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録の4つがセットで申立書になります。 |
|---|---|
| 債務名義の正本 | 強制執行の申立てをするには、債務名義の正本が必要です。 また、執行文が必要な債務名義ついては執行文が付いているかどうか確認してください。 執行文の付与や債務名義正本の発行は、債務名義を作成した場所(裁判所や公証役場)で行います。 |
| 送達証明書 | 債務名義の正本または謄本が債務者に送達されたことを証明する文書です。 債務名義を作成した場所(裁判所や公証役場)で発行します。 |
| 資格証明書 | 第三債務者が法人の場合、法人の商業登記事項証明書(代表者事項証明書)が必要になります。 |
| その他の書類 | 債権者や債務者の住所氏名が債務名義に記載されたものと異なる場合には、戸籍謄本、住民票、戸籍の附票などが必要になります。 |
| 収入印紙 | 4,000円 養育費の強制執行では、子ども(債権者)の数が増えると、その数に応じて収入印紙が必要になります。 |
|---|---|
| 郵便切手 | 3,000~4,000円 郵便切手の金額と組み合わせは、申立てをする裁判所によって異なりますので、申立てをする裁判所に確認してみてください。 |
強制執行の申立てのやり方を簡単にまとめると、下記のようになります。
申立書類に不備がなければ、申立が成立となります。
申立が成立すると、裁判所から、下記3者に対し「債権差押命令」が送られます。
第三債務者に債権差押命令が届いた時点で、銀行口座などは停止され、債務者は出金することができなくなります。
また、債権差押命令が元配偶者と第三債務者に送達されたときは、裁判所から債権者に対して送達通知書が送られてきます。
元配偶者に債権差押命令が送達された日の翌日から1週間を経過すると、第三債務者から差押債権を取り立てることができるようになります。
元配偶者の会社や口座のある銀行に直接連絡を取り、支払い方法などを相談します。
取り立てを完了した場合には、裁判所に取立完了届を提出して、養育費の差し押さえは終了となります。以上のような流れになります。
養育費の強制執行をする場合には、差押の対象財産として以下の3つが代表的なものとなります。
以下では、対象となる差押財産ごとに差し押さえの方法を説明します。
給料の差し押さえについては、以下5点を念頭においておくとよいでしょう。
一度給料の差し押さえをしてしまえば、債務者が会社を辞めるまでは差し押さえの効果は継続しますので、改めて強制執行を申し立てる必要はありません。
ただし、将来分の養育費を対象とする場合には、養育費の支払い期限後に支払われる給料からでないと取立をすることができません。
相手の会社から給料を取り立てる手続きに関しては、裁判所は関与しません。
自分で会社に連絡をして支払い方法や期限を決めることになります。
未払い額が大きく、毎月継続的に差し押さえる場合は、毎月の支払日を決めて振り込んでもらう形式がよいでしょう。
会社への差し押さえが競合した(他の債権者も差し押さえる)ような場合には、会社が差押分の給料を債権者に直接支払わず、法務局に供託する場合もあります。
その場合には、裁判所が供託金を債権者に配分する手続きをしますので、債権者は裁判所の発行する配当証明書を法務局に提出し、供託金の支払いを受けることになります。
もし仮に、会社が差押分の給料の支払いを拒否した場合には、会社に対して取立訴訟を提起して未払い分の養育費を回収します。
給料とは異なり、預貯金の差し押さえについては差押の範囲に制限がありません。
そのため、差押時点で存在するすべての預貯金が差し押さえの対象となります。
ただし、給料の差し押さえと異なり、将来の養育費に対して預貯金を差し押さえるということはできませんので、その都度、強制執行の申立てをする必要があります。
預貯金の差し押さえするときは、できるだけ残高が多いタイミングで行うことが効果的ですので、差し押さえのタイミングとしては給料日やボーナス支給日の翌日などがよいでしょう。
「債権差押命令」が金融機関に送達されると、対象となる預貯金口座は凍結され、出金ができなくなります。
金融機関に連絡をし、支払い方法や期限について話し合うようにしましょう。
給料や預貯金以外にも不動産や動産を対象として強制執行をすることができます。
しかし、不動産や動産を対象とする強制執行は、メリット・デメリットがあり、時間や費用がかかるため、まずは、給料や預貯金への強制執行を検討するとよいでしょう。
不動産に対する強制執行は、相手の所有する不動産を裁判所に競売してもらい、その売却代金から未払いの養育費を回収するという手段です。
不動産は売却できた場合には相当な金額になりますので、未払いの養育費が高額な場合でも一括で回収することができるというメリットがあります。
しかし、不動産に対する強制執行は、予納金というお金を裁判所に事前に納めなければならず、対象不動産の評価額によっては数十万円にもなることもあります。
また、競売が完了するまで半年以上期間がかかり、時間や費用がかかる点がデメリットです。
高価な貴金属などの動産に対する強制執行も、不動産と同様に裁判所に競売してもらい、その売却代金から未払いの養育費を回収するという手段をとります。
動産に対する強制執行は、不動産に対する強制執行と比較すると、換価までの期間は短いです。
また、予納金も低額で済むというメリットがあります。
もっとも、動産に対する強制執行の場合には、確実に売却できる見込みが低い点がデメリットです。
元配偶者が余程高価な動産を確実に所持している場合以外には実効性は低いといえます。
財産の差し押さえをして、第三債務者(会社や金融機関など)から、未払いの養育費を回収した場合には、裁判所に対して「取立完了届」を提出します。
これで、強制執行の手続きは終了となります。
強制執行では、①債務名義が必要で、②相手方の財産を特定する必要がある点、それ以外ではお金がとれない場合、会社がわからない場合がある点やメリット・デメリット、流れ、失敗しにくくなった点、将来分なども解説してきました。
申立後、銀行や会社と支払方法について相談したり、場合によっては申し立てても養育費の未払い額に足りないこともあります。
養育費の強制執行は意外と難しい手続きですので、まず一度、養育費に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
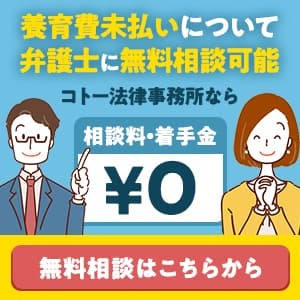
完全成功報酬制!相談無料!
完全成功報酬制!相談無料!